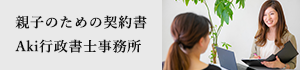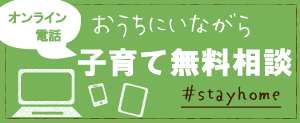ブログblog
スマホの危険性から考える対応策④
-
カテゴリ別
月別アーカイブ
-
-
ブログ2024.06.18
今日は、
④不適切なサイトに繋がる恐れ
について検討してみたいと思います。
スマホの危険性から考える対応策①はこちらから↓
不適切なサイトにアクセスすることによって考えられる具体的な問題として料金の問題と年齢制限の問題が挙げられます。
例えば、有害サイトから高額請求をされる恐れ。大人向けの不適切な表示や映像などを子どもが閲覧する恐れ。です。
では、どのような対策が有効なのでしょうか。
・不適切なサイトにアクセスできないようフィルタリングを設定する。
→常に監視をすることはできないので、フィルタリング設定で不適切なサイトを表示させないようにする。フィルタリングはスマホ等のデバイスごと、YouTubeやTikTokなどそのSNS単位でできるものもあります。一律に制限するタイプと、年齢ごとに段階に分かれ制限の内容がわかれているものも。年齢制限をかけることができるものも。フィルタリングと似た意味の言葉で「ペアレンタルコントロール」と表示されているものもあります。
・不適切なサイトについて日頃から子どもに話しておく。
→不適切なサイトというものがあること。そういったサイトはアクセスしただけで(登録はしていないつもりでも)ダイレクトメールや料金督促メール等、今までこなかったようなメールがくる可能性があることを事前に話しておく。時には脅すような内容のメールもあり、子どもは怖くなって一人でなんとかしようとしてしまうこともあるので、そういった際は、親に相談すれば対処できるから心配しないで言ってねと話しておくことが大切。

・新しくアプリをダウンロードしたい時等親に確認してからダウンロードするようにする。
→お子さんがどんなアプリを使っているか、お子さんの年齢にもよりますが、判断力が未熟なうちは把握できる環境が望ましいと思います。何でも親が管理、把握するのは過保護ではないかとの見方もあるかもしれませんが、ネット社会を善悪の判断が未熟なお子さん一人で歩かせることは相当のリスクが予想されます。極端な言い方ですが失敗が許されないのがネット社会です。お子さんのネットリテラシー(ネットを正しく使いこなすための知識)が養われるまではやはり親の判断を必要とするのではないかと思います。
ネットを使いこなす能力というのは、今までの教育にほとんど求められていなかったということもあり、親側としても何をどのように教える必要があるのか、わからないことも多いと思います。危険も多くあるというならお子さんをネットから遠ざけたくもなるかもしれませ。しかし、この急速なネットの普及と、望まずとも今後小学校、中学校、高校では一人1台のパソコン支給となり誰もがネットに触れざるを得ない環境に置かれます。そこで当窓口ではお子さまの年齢や状況に応じて、知っておいた方が良いと思われるネットの知識、社会のルールを様々な法律を踏まえて情報提供しています。
ご心配なことも沢山あると思いますが、そんなお悩みやご心配事をお聞きして一緒に考えるのが「親子のための保健室」です。
-
ブログ2024.06.18