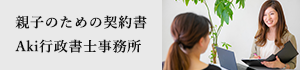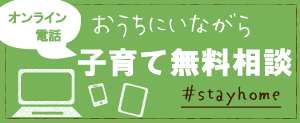親子のための契約書について
- HOME
- 親子のための契約書について
親子のための契約書とはabout pac
当サイトでは、子どものネットトラブルの対策を一緒に考えていきます。 分類してスマホトラブル・SNSのトラブル・ゲームの依存、の3つに区分しています。 ご家庭ごとにあわせた、お悩み解決に努め、親子の取り決めに法思考を踏まえて一緒に考えましょう。 その取り決めと、それに関わる法律(社会のルール)を、子どもでもわかる内容で記載して、 それをとりまとめたものが「親子のための契約書」です。
決まりはしばるためではなく守るために

「ルール」と言っても、子どもの自由をしばるためのものではなく、 子どもたちのネットトラブル等の被害から守るために定めるものだと思っています。 「契約書」という言葉も、冷たいイメージを与えるかもしれません。 しかし、「親が子を守るためのもの」という温かさをもっていると思ってみると、見方がかわりませんか? 「法律」という言葉も、縛るものととっつきにくいイメージもありますが、実は、社会における生活にとって身近なことであって、私たちを守ってくれる側面も持っているのではないでしょうか。
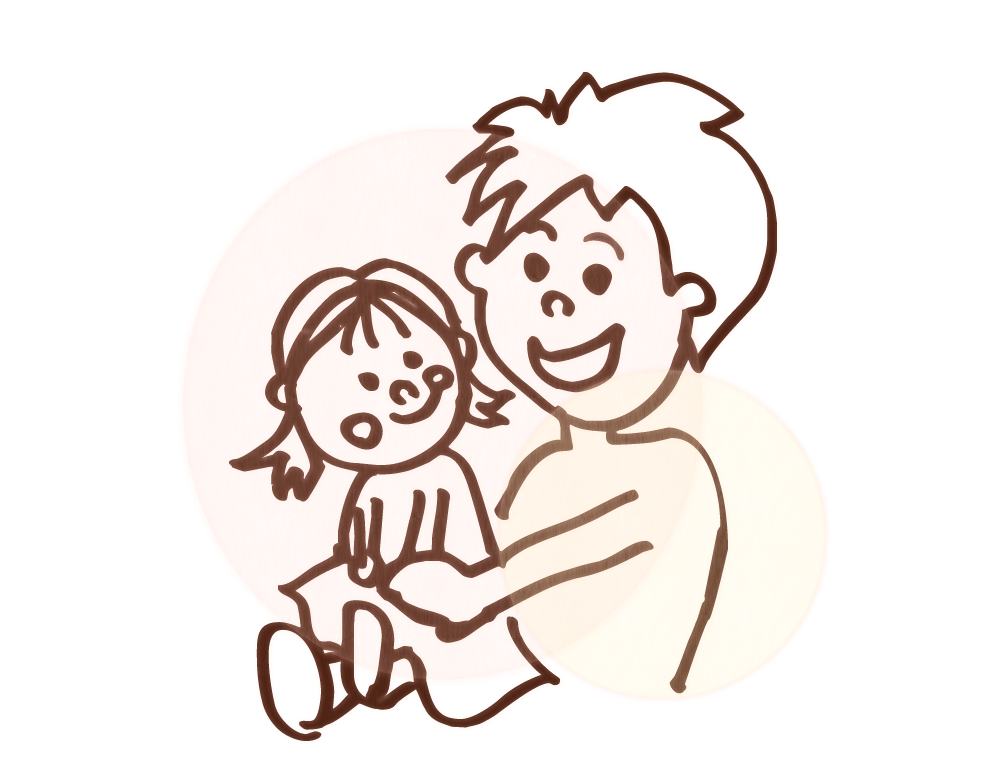
事前に対策をすることで守れるものがあります
このように、「親子のための契約書」は子どもたちの様々な問題(ネットトラブルや依存)から守るために、事前対策として、有効な策になり得るかもしれません。 【事前に対策を講じる】ということがこれらの問題には、とても重要なことに思えます。 ネットトラブルは、LINEいじめや誹謗中傷では子どもが深く傷つく恐れがあり、個人情報の投稿から個人を特定されてしまいストーカー被害に繋がってしまうこと、犯罪に繋がる恐れがあるのもこわいですね。 ふざけた動画を投稿してそれが炎上、拡散し、動画の削除がしきれなくなってしまったら一生ネット上に残り続けます。依存問題も、依存となってしまうと改善のための治療には親子ともに大変な労力や時間を費やします。こうなってしまう前に、十分なカウンセリングを行い、そのご家庭ごとに合わせた親子のための契約書を作成してみるのは、いかがでしょうか。 『親子のための契約書』の内容をどのようにするか決まりはありません。 カウンセリングを通して一緒に考えていきます。お子さまと一緒に育むことが何よりも大切なことなのです。 その為のツールとしてご利用いただければ、幸いです。
親子のための契約書の特徴
Point 1 子どもと対等の契約書
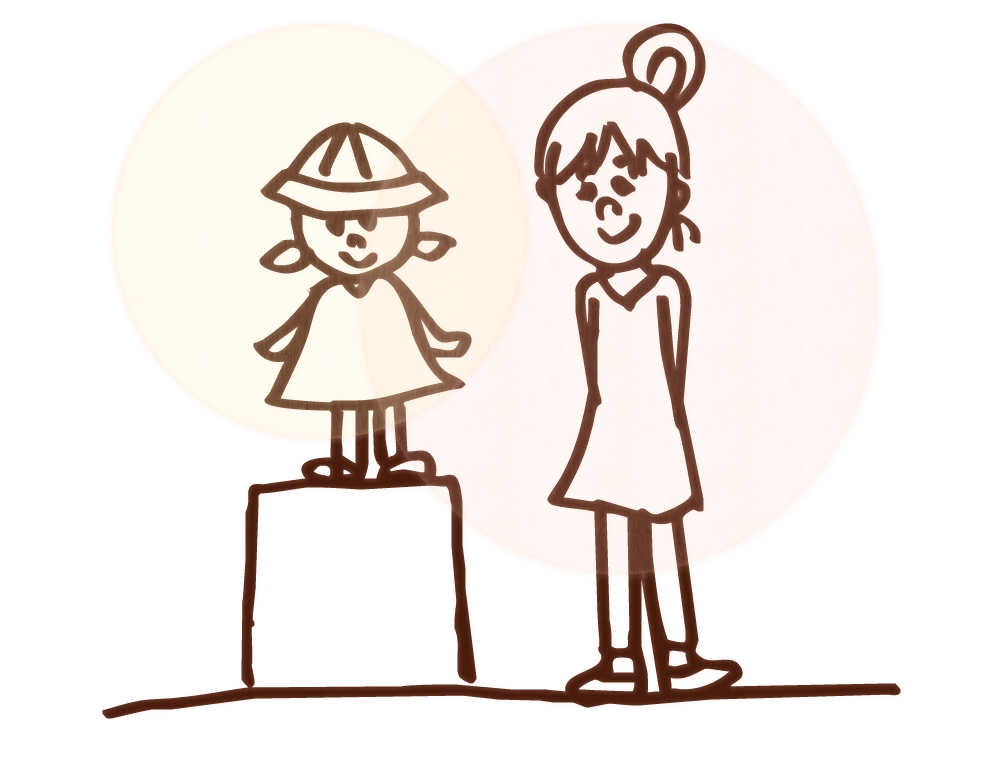
Point 2 ネットリテラシー対策のための契約書

ネットトラブルの当事者にならないために、知っておいてもらいたい法律や常識・倫理観を記載します。 また、お子さんのスマホやゲームの使用状況から考えられるトラブルや危険性などを私から注意を促すコメントも添えています。法律には触れなくてもトラブルとなるケースがあったり、依存の問題も深刻なので事前にしっかりと対策することが大切です。ネットリテラシー対策とは、ネット上の脅威の実態を知ることと、法律などの正しい知識を身につけること、さらに情報や誘惑に振り回されないマインドをもつことで高められると考えます。 「親子のための契約書」にはその要素を盛り込んでいます。 また記載されている法律とは、刑法・民法を中心として、関連した法律やいじめ防止対策推進法、著作権法、個人情報についてなど横断的に網羅しています。
Point 3 法教育を使って子どもの将来を守る契約書

法教育によって社会のルールを学び「契約をする」という体験を親子で経験することで、子どもたちをネットトラブルだけでなく、日常の様々なトラブルに対応できるようになることを目指しています。 そうやって子ども自身がトラブルを回避したり解決する力を身につけることが「子どもの将来を守る」ということに繋がると信じています。 ネット社会に出るために社会のルールを身につけたり、「親子のための契約書」で1人の人間として、親と約束することを体験することでネット社会に出る自覚や、自分の行動の責任感を養いますが、それらはすべて将来の子どもたちにとって必要なものといえます。 また、これを親子で経験することで親子の絆の再確認と、親子のコミュニケーションのきっかけとなることを期待しています。
社会のルールって何だろう?
法教育といっても法律はやはり難しく数も膨大で、もっと簡単に社会のルールを教えることは出来ないのでしょうか? 社会のルールをわかりやすく、一言でいうと? という問いに対して「他人に迷惑をかけない」という回答がみうけられます。 勿論間違いではないと思います。他人に一切の迷惑をかけていなければ、 恐らく社会のルールに反することはないのでしょう。 しかし、他人に一切の迷惑をかけないで生きていく事は困難です。人の権利とは何かを知る
言い方を変えると、みな他人に迷惑を掛けながら、支えあって生きているのではないでしょうか? 大人だからと言って、他人に一切の迷惑を掛けずに生きられる人なんているのでしょうか? 他人に迷惑をかけていい。子どもたちは、そういう考えが未熟でもいいのではないかと思います。 第一に大切なのは「他人の権利を妨害しない」ということを知る必要があります。 その人が本来持っている権利、これを妨害してはいけないという決まりがあります。 そして人の権利についても法律で定めています。ということで、他人の権利を妨害しないようにしようとしたら、何が人の権利なのかを知らないといけない。その為、法思考の必要性が高くなるのではないでしょうか?
ルールを知ることで自由度が広がる
少し面倒なようですが、法認識が明確になることで、結果的に「他人に迷惑をかけること」 を避けられることに繋がります。 今まで「他人に迷惑をかける行為」と思って遠慮していたことも「その人の権利を妨害しない行為」 なのであれば甘えてみてもいいんじゃないでしょうか。 それは広く捉えると、子どもたちの自由度が広がるということになるのではないでしょうか? そして、子どもの自由度を広げるために、法律(ルール)を知ると思えば、少しだけ法律に対する見方が変わると思いませんか。