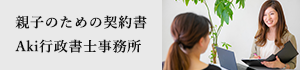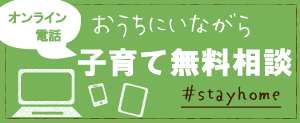ブログblog
ネットトラブルってなぁに?【後編】
-
カテゴリ別
月別アーカイブ
-
-
ブログ2024.06.18
子どものネットトラブル予防専門サイト
といっても、そもそも「ネットトラブルってなぁに?」
と思われる方もいらっしゃると思います。
前回に引き続き、ネットトラブルの分類と危険性について
後編をお届けします。
3.違法性の問題
ネット上で違法性を帯びる(人を傷つける)発言をしてしまう、モラルを欠いた動画を投稿してしまう、などです。
ネット上で、社会のルールに反すると、大人も子どもも関係なく、ネット上で制裁を受けることがあります。
また、子どもがしたことであってもその損害賠償を保護者である親に請求がくる、ということもあります。
今まで家庭と学校の中だけで生活してきたのと違い、ネット社会に出るのであれば子どもも社会のルールを守らなければなりません。
つまり子どもが社会のルールを知ることは、自分で自分の身を守ることに繋がります。
法律違反があった場合、
「そんなルール(法律)があるなんて知らなかった」
「他の人もやっていたので、良いと思った」
では済まされません。ネット上で第三者とトラブルになると、弁護士を介して“裁判”となるなど、大きな問題に発展してしまうことがあります。
「ゲーム実況を、YouTubeにアップロードした人が刑事告訴される」
「Twitterの、いいねやリツイートで訴えられる」
「便乗して、誹謗中傷の投稿をする」
など、たくさんあります。

4.料金の問題
課金やWi−Fi環境下では無いところでの、長時間の利用による高額請求の問題です。
課金は家庭のルール内であれば良いと思います。
今は誕生日プレゼントが【課金】と言う家庭もあり、そういう時代なのだと思います。
課金自体が問題というより、金銭感覚が希薄な子どもは、課金に対して、実際“お金を使っている感覚”が無く、どんどん課金を繰り返し、何十万〜数百万の請求が来た、と言うケースがあります。
また、課金を繰り返すことで例えばオンラインゲーム上で”良い装備”を手に入れゲームを有利に進められる人は周りのプレイヤーから慕われて、課金がやめられなくなる。
という人もいます。課金するお金欲しさに事件を起こしてしまったケースもあります。
オンラインゲームのガチャやスキンの購入、アバター作成のための課金など。
5.情報の正誤判断が出来ないコトによる問題
正しい知識が無い故に、悪意のある第三者に“騙されてしまう”問題です。
オンラインゲームや、SNSで知り合った人と仲良くなり(正しくは、仲良くなった“気”になり)、連れ去られてしまう事件が増えています。
去年は小学1年生の女の子が、わいせつ写真を送らされるなどの事件もありました。
詐欺メールや不適切サイト、なりすましは“そういったことがある”ということを、知らなければ、大人でも騙されてしまいます。
逆にいうと「そういうことがあるかもしれない」という知識があるだけで防げるのです。
連れ去り、児童ポルノ、詐欺メールや有害サイトなど。
【ネットトラブル】と言われると、キリが無いほど多くの問題があるように思えますが、分類するならこの5つのどれかです。もしくは、複数が重なっているような場合です。
意外とシンプルだと思いませんか?そして、このトラブルを具体的に知るだけでも、防げることはたくさんあると思います。
ぜひ、ネットトラブルの具体例についてお子さんと共有してもらいたいと思います。
うちの息子には「オンラインゲームのボイスチャット禁止」というより
「オンラインゲームで知り合った人に連れ去られてしまった事件があるんだって」
と話したら、息子が自分で
「それは怖いからボイスチャットはやらない」
と判断しました。
もちろんお子さんの気質によって様々ですが、伝え方や伝える内容を工夫するだけで子どもの意識が変わることはありますよね。
うまくいかないなーということがあればぜひご相談いただければと思います。
お悩みが解決するまで一緒に考えます。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました(^ ^)
-
ブログ2024.06.18