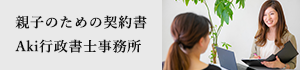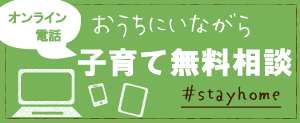ブログblog
法教育について⑤「こども六法」
-
カテゴリ別
月別アーカイブ
-
-
ブログ2024.06.18
法教育に対して私の考えや例えなどをご紹介してきましたが、実際の法教育はどうに教えるの?どんな法律を知る必要があるの?
という点について、今日は書いていきたいと思います。
まず「親子のための保健室」内の記事でもブログでも、私はあまり実際の法律の内容については触れていません。法教育ってどんなものか、であったりそれを知ることでどんなメリットがあるかを何度も説明していると思います。
これはなぜかというと、法教育では「法律の考え方(法思考)」を身につけることが最も大切なことだと思っているので個別の条文ではなく、法律全体に興味をもってもらいたいなと思っているからです。
そして私の役割とはまさに「法律に興味をもってもらうこと」なのではないかと思っているからです。
法律の中身を知りたくなったらネットでも書籍でも簡単に見ることができるので、私はそこに至るまでの橋渡し役でありたいなと思っています。
でも実際にお子さんが法律に興味をもったとしても、いえ、お子さんだけでなく親御さんであっても、実際の法律の条文そのままをみても最初はちんぷんかんぷん。読む気もうせてしまうでしょう。
私も今でこそ慣れましたが、行政書士の資格取得のために勉強を始めたばかりのころは、とにかく法律用語が難しく、言い回しがくどいというか何が言いたいのかはっきりしないようなもやもやした気持ちで勉強していました。
今となってはそのくどい言い回しも、この言い方しかなかったんだなと理解できるし、法律用語も慣れましたがそれでもエッセイやミステリー小説のようにさくさく読み進められるようなものではありません。

そこで、親子で読むのにお勧めの法律の本をご紹介します。テレビや雑誌でも多く取り上げられているのでご存じの方も多いと思いますが、山崎総一郎著書の「こども六法」です。当サイトの法教育のページでもご紹介しています。
こちらの本は法律の中でも子どもたちの身近な法律に絞って、条文数も大事なところだけに絞って掲載しているので網羅的に色んな法律の知識を身につけることができます。こういった書籍があるので、実際の法律の話しはここにお任せをして、私は法律に興味と親しみを持ってもらうことに専念できるのです。
ただ、この「こども六法」は、10歳くらいからのお子さんに読まれることを想定して作られるためそれより年齢の低いお子さんは親御さんに読んでもらって説明をしてもらわないと難しいと思います。
私の取組みでは法教育は未就学児から小学校の中学年くらいまでに始められることを推奨している為、その年代の子どもたちが一人でも読める本(絵本?)も必要だなと感じています。もちろんその本を親子で一緒に読んで頂きたいのですが、お子さんだけでも読めるようなものがあるといいなあと切実に思っています。
今日は実際に法律に興味を持ったら「こども六法」がおすすめですよ。というお話しでした。
もちろん私のカウンセリング時や「親子のための契約書」には法教育の話しが詰まっています。
そのお子さんごとに、年齢や扱っているデバイス(スマホなのかゲーム機なのか)親御さんの心配事に合わせて法律をチョイスしてまずは最低限のところから少しづつ身につけて頂けるようなステップをご用意しています。
-
ブログ2024.06.18